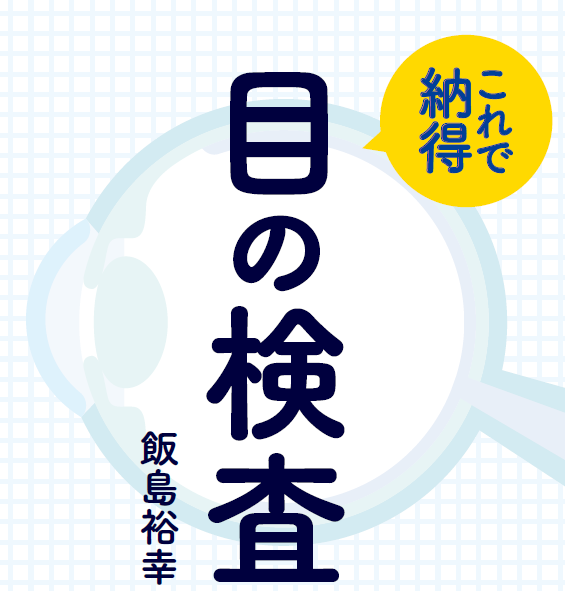メガネ処方の疑問:ORT編
- 山梨の目医者
- 2025年2月7日
背景
2025/2/18開催予定の山梨大学眼科学習会で[メガネ指導と処方]のレクチャーを予定していますが、その準備のために視能訓練士ORT(Orthoptist)の方々にアンケート調査を行いました。
その中の質問:[メガネ処方をする際に困ることなどあれば自由記載でお願いします]に多くのご意見をいただきましたが、レクチャーでそのすべてについて解説するのは難しいのでここに掲載しました。
[遠近両用メガネ(累進メガネ)]に関して
ORTから:[患者本人が今まで遠近を使っていたので累進焦点を希望されているが、明らかに近用が使用できておらず装用練習の場では見えるとの回答があるが、作成後に見えないなどのトラブルにつながる可能性が予想されるとき。]
ORTから:[遠近両用累進メガネ処方についてです。視野障害や累進眼鏡を使い始めるご年齢が高齢なため、単焦点を勧めましたが、ご本人の強いご希望があり処方しました。処方後ご希望の見え方にならず、単焦点に直して再処方となった事があります。]
回答(上記2件に対して):高齢者に多い問題点です。[累進メガネは、朝顔を洗った後から夜寝るまで1日中掛けて常用することが基本で、そのような使用訓練を続けた後に、はじめて視線の上下移動に慣れて近くも見やすくなる]という理解が重要です。その理解が難しい高齢者には遠用と近用の2つの単焦点メガネを所持してもらい、その都度掛け替えてもらうのが無難です。(あるいは買い物などで値札を読むくらいはできる低加入度の累進メガネと読書用の単焦点近用メガネの掛け替えでもよいでしょう。)

ORTから:[累進眼鏡にフレネル膜は、組み合わせとして良いのか悩みます(強く希望する方がたまにおります。]
ORTから:[複視がありプリズムの装用が必要だが患者から強い遠近処方の希望がある場合。]
ORTから:[遠近両用にプリズムを組み込む際に、装用練習での見え方が実際と異なることが多く、作成していただいて確認してもらうことがおおくなってしまう。]
回答(上記3件に対して):片眼のプリズム度数が2-3△(プリズムジオプター)までなら累進+プリズムの組み合わせでよいかもしれませんが、それでも最後の質問者のように再作の可能性を説明してから処方するのが無難だと思います。]
[乱視矯正]に関して
ORTから:[斜乱視の装用感が悪い時のおとしかた(はどうすればよいか?)]
回答:多少矯正視力が出にくくても乱視度数が一番小さく円柱レンズ軸も180/90度に一番近いところで決定するのがよいでしょう。
[不同視]に関して
ORTから:[単眼の白内障手術が終わった後に使用する眼鏡の作成で不同視が出ている時(どうすればよいでしょうか?)]
ORTから:[左右で屈折値の差があるときにどうするか。]
回答(上記2件に対して):不同視差が1.5~2.0D以内ならそのとおりに矯正して両眼視できるでしょう。それ以上の不同視の場合はプラス側の目にそろえて処方します。そうするとマイナス側の目は近視状態なのでモノビジョンを実践できて近用メガネが不要になる可能性があります。
[眼病変のある患者のメガネ]に関して
ORTから:[病気のために視力がでにくいのに、眼鏡をかければ見えるようになると思っている方(にどう対処すればよいか困る)。]
ORTから:[網膜病変で中心に歪みがある方への眼鏡で矯正できないことの説明(をどうすればよいか?)]
ORTから:[免許更新通らず何回かトライしている方(完全矯正でも基準の視力足りない方) ]
回答(上記3件に対して):主治医の眼科医に説明してもらうしかないでしょう。
ORTから:[日により度数に変動ある人の処方度数の落とし所(はどうすればよいか?)]
回答:これは免許更新目的の軽度白内障患者さんに多いケースです。乱視度数が小さく円柱レンズ軸も180/90度に近い処方で最終決定します。さらに患者さんには[一番見やすいレンズ位置をさがすように]と指導しておくのがよいでしょう。
[その他]
ORTから:[眼鏡合わせ検査時、矯正視力0.7届かない患者さんが「先生に眼鏡を替えれば免許更新ができると言われた」と発言あり、中々免許更新が難しい事を受け入れられない。]
ORTから:[「先生に眼鏡を作れと言われた」など理解が乏しく本人が眼鏡を作る意図が曖昧で眼鏡合わせをして処方箋を出しても結局眼鏡を作らない。]
ORTから:[装用練習中の自覚が曖昧な患者さんに対し、どの程度度数を調整するか悩ましいです。例えば、完全矯正値では違和感があるが、度数を調整してもあまり変わらず現在使っているJBと同じ視力値まで下がってしまい、改めて完全矯正度数と掛け比べてもらうと、完全矯正値でも掛けられると仰ったりします。また、成人している方では掛けられないような度数なのに、掛けられると仰る患者さんもいます。そのままでは処方せず、運転時に困らない視力を保つ程度に弱めて処方しますが、どこまで患者さんの自覚や反応を鵜呑みにしていいか悩みます。
回答(上記3件に対して):メガネのことがよくわかっている眼科医に相談してもらうことをすすめます。]