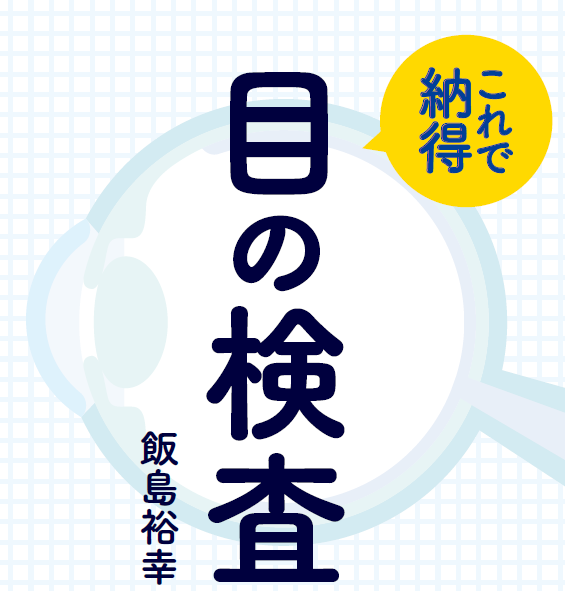肥厚性硬膜炎と梅毒
- 山梨の目医者
- 2024年12月9日
脳や脊髄の硬膜が慢性炎症によって肥厚する肥厚性硬膜炎(Hypertrophic pachymeningitis: HP)の臨床的特徴は頭痛と種々の神経症状(脳神経麻痺、小脳失調、対麻痺など)です。https://www.nanbyou.or.jp/entry/3202
診断には造影MRIが有用で脳硬膜が肥厚して造影されます。
HP患者はうっ血乳頭や複視、視力低下で眼科を初診することもあります。https://meisha.info/archives/2794
続発性HP
HPには原因不明の特発性以外に、表に示す種々の原因による続発性HPが知られています。
野倉一也 他: 肥厚性硬膜炎. 眼科 63:1469-76.2021
このうち感染症に関しては梅毒血清反応(RPR, TPHA)、T-SPOTやQFTなどの結核に対するインターフェロンγ遊離試験(IGRA:interferon-gamma release assay)、β-D-グルカンや真菌抗原などの検査が必要です。
自己免疫疾患に関してはANCAを含めた膠原病関連の自己抗体検査が必要です。
またIgG4値を血液検査で調べる必要があります。

症例:73歳男性
Yさんは右の眼痛と視力低下を訴えてF病院眼科を受診し、中心フリッカー(CFF)値の低下から球後視神経炎を疑われて大学病院眼科を紹介されました。
RAPDは右で陽性で、右中心視野の耳側暗点が固視点に及んでいました。
びまん性の硬膜肥厚が造影MRIで示され、梅毒血清反応が陽性だったため、梅毒による続発性HPの疑いで神経内科に紹介されました。
神経内科で行った髄液検査では細胞増多がみられ、Treponema pallidum抗体を検出するFTA-ABSが陽性でした。
しかし血液検査では、MPO-ANCAも陽性で、IgG4も高値(161mg/dl、正常:11-121)でした。

HPの原因精査目的で脳外科にて脳硬膜の生検を行いましたが、線維性肥厚を示すものの血管炎の所見やIgG4陽性形質細胞はみられず、HPの原因について、梅毒、ANCA関連血管炎、IgG4関連疾患、いずれであるかの結論は得られませんでした。
しかし髄液検査結果から中枢神経への梅毒感染が示されているので、入院して強力なペニシリンG点滴治療を2週間行いました。
その結果、右眼の視力は1.0に改善して視野もほぼ正常化しましたが、MRIでの硬膜肥厚は不変でした。
その後の経過
その半年後、今度は左眼の外転神経麻痺による同側性複視を訴えて受診しました。

そこで神経内科に入院にてステロイドパルス治療を2クール行ったところ、眼球運動は改善し今度はMRIでの硬膜肥厚の所見も改善しました。

HPの原因に関して
初診時の右視神経障害と半年後の左外転神経麻痺のうち、前者は梅毒による続発性HPが原因と当初は考えましたが、ペニシリンG点滴治療で硬膜肥厚の改善なしに視力視野が改善したので、視神経の梅毒による直接障害が原因だったのではないかと考えています。
(ただしRPRとTPHAの定量値は前者が4x~8x、後者が80x~160xの間で推移して有意義な変化はみられませんでした。)
一方、左の外転神経麻痺はステロイド治療で硬膜肥厚の改善とともに軽快したことから、HPによるものでその原因は自己免疫性または特発性の要素が強いと考えられました。
梅毒がHP発症にかかわったかどうかは今回のケースでは不明でした。