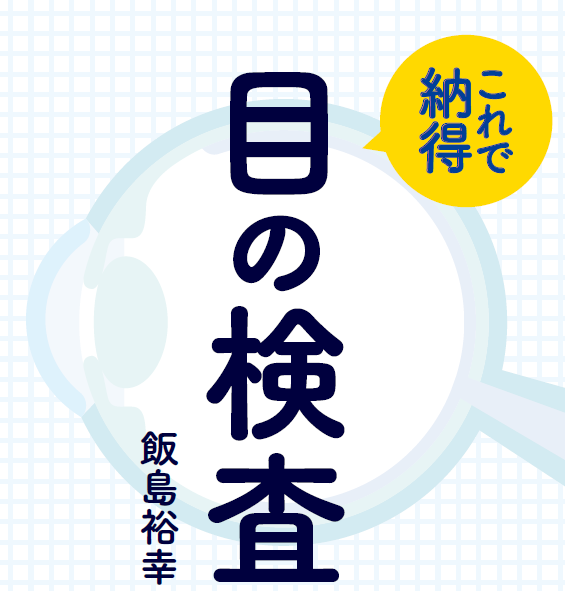緒言と考按
- 山梨の目医者
- 2025年5月16日
入局1-2年目の若手眼科医は担当した興味深い症例を医局内の会や地方学会で発表します。
その際パワーポイントPPTで作成する緒言、症例、考按、結語(まとめ)のうち[緒言]と[考按]の違いがわからないという声をきくことがあります。

研究論文の緒言と考按
ちなみに医学雑誌に投稿する基礎あるいは臨床研究の論文も[緒言]と[考按]を含めた構成になりますが、山口大学の教授だった西田輝夫先生は[緒言には論文のメッセージと報告の価値を過去の研究を整理しながら明記する]と書いています。
西田輝夫: 説き語り論文作法2.緒言にかくべきこと. 臨眼 63:648-51.2009
また[考按の最初には、論文の一番のポイントである結果のまとめを示し、最後の段落で研究の意義や展望を書く]としています。
西田輝夫: 説き語り論文作法9.考按の構造. 臨眼 63:1867-73.2009
症例報告発表
症例報告でも考え方は似ています。
緒言の目的は発表する疾患についての学会でのコンセンサスを示すことで、ガイドラインや綜説論文を要約した疾患の概略を客観的事実として示します。
一方、考按で示すのは、今回の症例の経験を通じて発表者が伝えたい主観的な意見です。
その際に、得られた知見の新規性や所見の解釈、病態の考察などを論じることになります。

具体例
症例報告の具体例として[梅毒による黄斑部病変ASPPCの1例]https://meisha.info/archives/5534という発表の緒言スライドを示します。
ここではASPPCがAcute syphilitic posterior placoid chorioretinitisという長い英文病名の頭文字を並べたものであること、有名なGass先生が眼梅毒の黄斑部病型として6例報告した際に命名されたこと、さらに2期梅毒でみられる眼部病変のうち後部ぶどう膜炎の特殊病型であることを1枚のスライドにまとめました。

症例の病歴や所見、経過のスライドは省略しますが、考按では視力予後について考察します。
ASPPCについての最近の多数例の報告では、早期にペニシリンの全身投与を開始すれば、多くは1.0の最終視力になるとされています。
しかし発表症例では0.3/0.7という最終矯正視力に終わりました。
その理由として初診時にAZOORと誤診して2週間ステロイドを全身投与したことが病原体に対する免疫機能を低下させたのではないかという推測を考按で示しました。