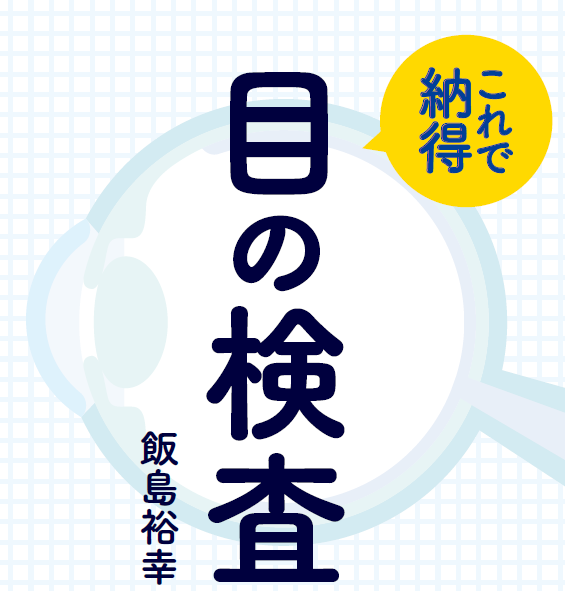先天縮瞳
- 山梨の目医者
- 2024年10月18日
先天縮瞳は暗所でも1mm程度の高度の縮瞳が両眼にみられる状態で、トロピカミドやフェニレフリン(ネオシネジン)などの散瞳点眼薬https://meisha.info/archives/4375にもほとんど反応しません。
古くから家族性と孤発例の報告があり、組織学的検討では瞳孔散大筋の先天的な低(無)形成が原因とされています。
佐堀彰彦, 他: 緑内障を合併した先天縮瞳の兄弟例. 日本眼科紀要 38:853-7.1987
高柳芳記, 他: 先天縮瞳の兄妹例. 眼科臨床医報 83:1088-92.1989
中井義秀, 他: 先天縮瞳の1例. 臨床眼科 45:1105-9.1991
症例:11歳男児
学校の検査で視力不良を指摘されて近医眼科診療所を受診しました。
RV = 0.7 (1.0 X -1.25D)
LV = 0.8 (1.0 X -0.75D)
軽度の近視以外に両眼の高度の縮瞳を認めたため、精査目的で大学眼科を紹介されました。
両眼の瞳孔径は1mmで色調は淡く、虹彩紋理は消失しています(図上段)。
前眼部OCT(カシア)https://meisha.info/archives/826では瞳孔縁を除いて虹彩の菲薄化が明らかです(図下段)。

暗所で倒像検眼鏡を用いて対光反応をみるとわずかに瞳孔が動きました。
眼瞼下垂、瞼裂狭小はなく、梅毒血清反応は陰性で、両親には縮瞳はみられていません。
散瞳薬への反応
まずネオシネジンを点眼しましたが、散瞳せず、次いでサンドールP(トロピカミドとフェニレフリンの合剤)を点眼すると瞳孔径は1.5mm程度に拡大し、対光反応は消失しました。
しかし眼底観察は超広角眼底カメラ(オプトス)https://meisha.info/archives/4400にても不可能でした。
1週間のアトロピン+ネオシネジン点眼後
1%アトロピン点眼+ネオシネジンの1日2回1週間の点眼指示後の再診で、両眼とも瞳孔径は3mm程度に拡大し(図左半の上が初診時、下が再診時)、オプトスにて眼底検査もかろうじて可能でした(図右半)。

なお本人に尋ねたところ近見でやや見えにくい自覚があったとのことで、アトロピン点眼での毛様体筋麻痺による調節障害と考えられました。
しかし不自由はなく、瞳孔径が3mm程度といまだ縮瞳状態のため、焦点深度効果で軽度の近方視障害にとどまったためと考えられました。